|
幸せにしてくれる大切なモノたち
|
・DTEとDCE間の接続プロセスを定義
・通信事業者のフレーム・リレー網内部でのデータ伝送方法は定義せず。
・OSI参照モデルのデータリンク層で動作し、コネクション型プロトコル
・V.35、X.21、EIA/TIA-232、EIA/TIA-449は
フレームリレー接続をサポートしているインタフェース(物理層)
・フレームリレーではVC(Virtual circuit:バーチャルサーキット)と呼ばれる仮想回線を使用
・PVCは常時接続環境を実現し、SVCは必要に応じて回線を確立する。
・各VCを識別するためにDLCI番号を使用する
・グローバルDLCI番号はフレームリレーもう全体で一意に識別される
・ローカルDLCI番号はローカルのDTEとDCE間でのみ識別される
・ローカルDLCI番号と宛先ネットワーク層アドレスを対応付けた、
フレーム・リレー・マップを参照してデータを送信している
・フレーム・リレー・マップは手動で、またはInverse ARPで動的に作成
・フレーム・リレーでは、エラー訂正はTCPなどの上位層プロトコルに依存する
・フレーム・リレーはX.25の後継プロトコルである。
・フレーム・リレーはITU-TとANSIで標準化されている
・LMIとは、DTEである顧客側ルータとDCEであるフレーム・リレー・スイッチとの間のシグナリング方式を定義
・LMIはキープアライブ機構、マルチキャスト機構、ステータス機構が提供される
・キープアライブ機構は、
PVCの状態を確認するためにDTEからDCEに10秒ごとにキープアライブを送信する機能
DTEは30秒間のホールドタイマを設定している。
・ステータス機構とは、DTEからキープアライブを受信したDCEが、PVCの状態を通知する機能
・PVC確立後、Inverse ARPは60秒に一回交換される。
・DTEとDCE間で使用するLMIタイプは同一のものでなくてはならない
・LMI識別子として、cisco、q933a、ansiがある。
・CIR(認定保障速度)とは最低保障帯域のこと。フレーム・リレーを利用する顧客はもう何の帯域幅を確保するために、
エンドツーエンドで最低限保障される通信帯域に基づきて契約される。
・FECNとは、フレーム・リレー網内で逼迫が発生した場合に、
網内のフレーム・リレー・スイッチがFECNビットに1をセットして宛先ルータに送信して
現在逼迫状態であることを知らせる。
・BECNとは、フレーム・リレー網内で逼迫が発生した場合に、
網ないのフレーム・リレー・スイッチがBECNビットを1にセットして送信元ルータに送信して
現在逼迫状態であることを知らせる。
BECNを受信したルータあは、フレームの送信速度を落とす。
・NBMA(Non-Broadcast Multi-Access)とは、
マルチアクセスなのに(複数のルータが接続されている環境のこと)ブロードキャストを送らない
(ルーティングアップデートなどで、ブロードキャストで送られているはずのものが、
このネットワークのしくみにより、すべてのルー ターに行き渡らない)
1つのインタフェース(もしくは1つのサブインタフェース)上 で、
同じサブネットに属しているPVCがいくつもあるときに発生
スプリットホライズンの機能によって、他DCEに経路が候補されない
キャリアのネットワークに接続するために必要な装置
アナログ網に接続するためにDCEとして、「モデム」を利用 例としてADSL
デジタル網に接続するためにDCEとして、「DSU」を利用 例としてISDN
・DTE(データ端末装置)
DCEを通じて網に接続して、実際に通信を行う機器のことを指しています。
DTEの例としては通常のコンピュータやルータなど
~通信の流れ 拠点Aから拠点B~
拠点A DTE--->DCE---->|------>キャリアの網------>|--->DCE--->DTE 拠点B
・DCEは、クロックと呼ばれる電気信号をDTEへ送って通信の同期をしている。
・現実のWAN環境ではクロックの設定は通信事業者が行う。
・ラボ環境などでルータ同士をSerialケーブルで直接つないだ
場合(バックツーバック接続)には、 クロック信号を発信する側を決める。
・クロックの設定が行われていない場合、DCEとDTEは通信できない。
・通常はSerialケーブルの両端のコネクタ部分に、
そのコネクタがDTEとDCEのどちらであるかを表すラベルが貼られている。
ルータのSerialインタフェースは、コネクタが接続された時点で、
自分がDCEとDTEのどちらであるかを認識します。
・コマンドで確認する場合は、show controllersで確認できる。
・DCE側のSerialインタフェースに下記クロックの設定をおこなう。
Router(config)#interface Serial 0/0 ←DCE側のSerialインタフェースを指定
Router(config-if)#clock rate 64000 ←64kbpsのクロックを設定
Router(config-if)# bandwidth 64 ←帯域幅を64kbpsに設定
※bandwidthコマンドはkbps単位
※clock rateコマンドはbps単位
bandwidthコマンドで設定された値は,回線の実際の帯域に影響を及ぼしません。
IGRP,OSPF,EIGRPなどのルーティングプロトコルのメトリック計算に使用されます。
・参考にしたサイト
www.n-study.com/network/2002/08/dcedte.html
itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20051206/225733/
・参考にした本
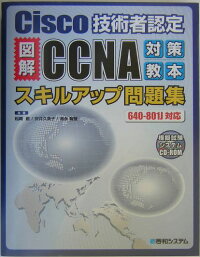
図解CCNA対策教本スキルアップ問題集
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
お笑いが大好きな人です。
映画・音楽・読書も好きな人です。
お酒とタバコが好きな人です。
1984年生まれの人です。
